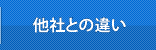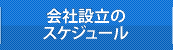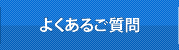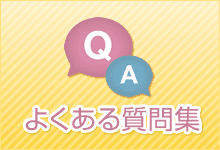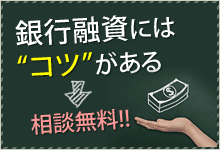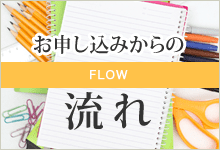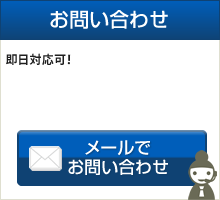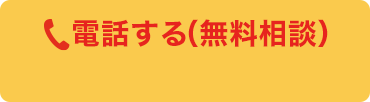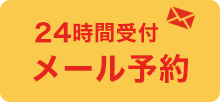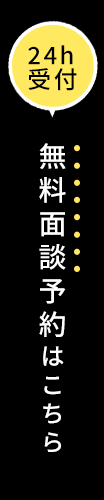合同会社設立の流れ。自分でもできる?手続方法や必要書類を解説
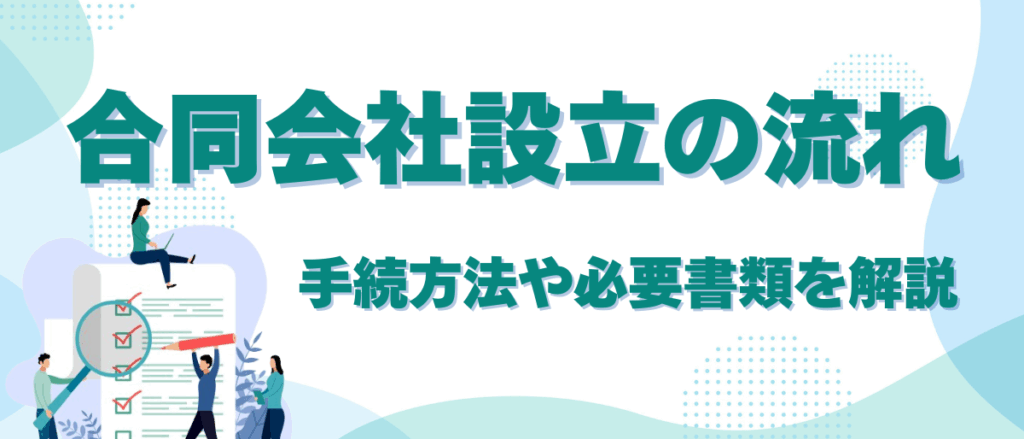
はじめての合同会社設立は「何から」「どこまで自分でできるの?」が最大の悩み。
この記事は、合同会社(LLC)の設立手順・必要書類・費用・期間を、初心者にもわかりやすく整理。
さらによくある失敗と回避策、専門家やクラウドを使う判断軸まで一気に解説します。
合同会社とは?会社設立の基礎知識
合同会社と株式会社の違い
会社設立を検討する際に多くの方が迷うのが、「合同会社にするか、株式会社にするか」という点です。
それぞれの形態には特徴があり、事業規模や将来の方向性によって最適解は異なります。ここでは、代表的な違いをわかりやすく整理します。
所有と経営の一体性
合同会社は、出資者がそのまま経営者(社員)となる仕組みです。
たとえば、3人で出資して設立した場合、その3人が基本的に経営の意思決定を行います。
そのため決断が早く、スタートアップや小規模ビジネスに向いています。
一方、株式会社は株主と取締役(役員)が分かれており、大きな会社になるほど経営と所有が分離される傾向にあります。
資金調達力やガバナンス(組織的な経営管理)の強さが魅力です。
対外的な信用・資金調達
銀行融資や大企業との取引では、株式会社の方が有利になるケースが多いのが実情です。
たとえば、「上場を視野に入れる」「VCから資金調達をしたい」といった場合は株式会社の形態が不可欠です。
ただし、合同会社でも業種や相手先によっては問題なく信用を得られるケースもあり、実際にIT系やコンサル業などでは合同会社の採用例が増えています。
設立・維持コスト
コスト面では合同会社が圧倒的に有利です。
合同会社の登録免許税は最低6万円で済み、定款認証(約5万円程度)が不要のため、初期費用を抑えられます。
一方、株式会社は登録免許税の最低額が15万円に加え、定款認証費用が必要となり、設立時点で20万円前後は見込む必要があります。
維持コストも決算公告義務などの点で株式会社の方が高くなりがちです。
意思決定の柔軟さ
合同会社は内部自治が柔軟で、利益配分も出資比率に縛られません。
たとえば「出資は1割だが実務貢献が大きい人に多めに配分する」といった設計も可能です。
これは、少人数で役割分担を明確にしたい場合に大きなメリットとなります。
株式会社は出資比率に応じた配当が原則であり、透明性が高い反面、柔軟な分配はしにくい仕組みです。
合同会社が選ばれるメリット・デメリット
メリット
- 設立費用が低い、スピード設立しやすい
- 意思決定が速い、利益配分が柔軟
- 小規模〜中規模ビジネスの機動力に合う
デメリット
- 業種や相手によっては株式会社より信用力で見劣りする場合あり
- 「採用・対外PR・資金調達」で株式会社を求められる場面がある
個人事業主が法人化する際に合同会社を選ぶケース
- 少人数で素早く事業を回したい(IT、クリエイティブ、専門サービスなど)
- 設立コストを抑えて試しながら拡大(後に株式会社へ組織再編も可)
- 利益配分や意思決定の柔軟さを重視(創業メンバーの貢献度で配分)
合同会社設立の流れ
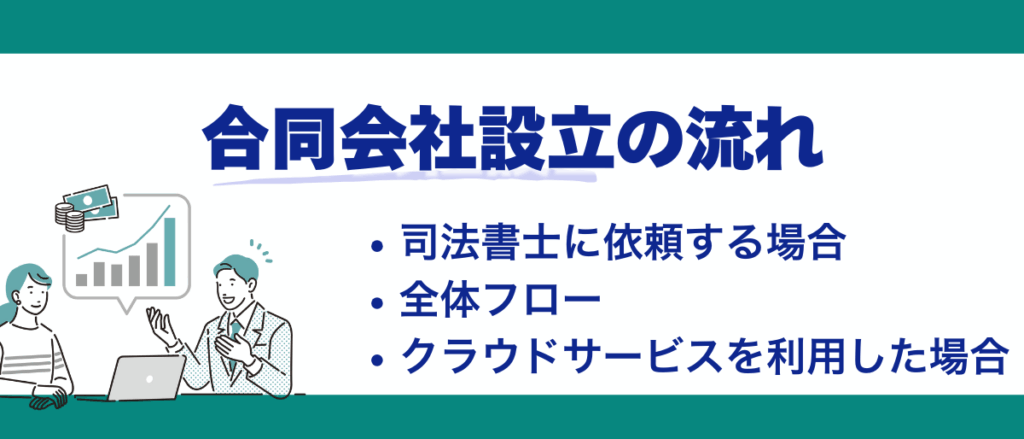
設立までの全体フロー(計画 → 定款作成 → 登記 → 税務・社会保険届出)
-
1. 事業計画・資本金設計・社名/目的決定
2. 定款作成(電子推奨)
3. 出資払込(通帳で証跡確保)
4. 登記申請(法務局)
5. 税務・社会保険・労働保険の届出
6. 口座開設・会計/請求の運用開始
自分で設立する場合の流れと司法書士に依頼する場合の違い
- 自分で:最安だが、定款・登記書類の作成でつまずきやすい。期日管理・書類不備の手戻りに注意。
- 司法書士:定款・登記のプロ。不備リスクを下げ、スケジュール短縮が見込める(手数料は上乗せ)。
freeeやマネーフォワードなどクラウドサービスを利用した場合の流れ
- ガイドに沿って入力→電子定款→登記書類の作成がスムーズ。
- そのまま会計・請求・経費精算まで運用を一体化できるのが強み。
- 司法書士連携プランで「自分+専門家」のハイブリッドも可。
合同会社設立に必要な書類一覧
設立手続きで準備すべき書類を区分ごとに整理したので、提出先や期限の最新案内を確認しながらチェックしてください。
| 定款 関連 | 定款(電子/紙) | 合同会社は公証役場での認証不要。電子なら収入印紙0円、紙は4万円が必要。 |
|---|---|---|
| 登記 関連 | 登記申請書/代表社員の就任承諾書/本店所在地決議書 など | 登録免許税:資本金×0.7%(最低6万円)。添付書類の体裁ミスに注意。 |
| 個人 書類 | 代表社員・社員の印鑑証明書、本人確認書類 | 直近発行の印鑑証明書を用意。 |
| 印鑑 | 法人実印・銀行印・角印(任意) | 電子印鑑・クラウド契約との併用が便利。 |
| 税務 | 法人設立届出書/青色申告の承認申請書/給与支払事務所等の開設届出書 など | 青色は原則、設立日から3ヶ月以内等の期限。最初に押さえる。 |
| 社会 保険 | 健康保険・厚生年金新規適用届、被保険者資格取得届 | 役員のみでも適用になるケースあり。採用予定なら早めに準備。 |
| 労働 保険 | 労働保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届 など | 従業員採用時に必要。期限は概ね5〜10日前後が多い。 |
| 注意 | ※書式・提出先・期限は地域や体制で異なる場合があります。 | 必ず最新の案内を確認してください。 |
合同会社設立の費用と期間
設立に必要な費用の内訳(登録免許税・定款認証費用・印鑑作成など)
設立費用は項目ごとに仕組みが異なります。
以下の表では、合同会社の設立に必要なおもな費用を内訳とあわせて整理しています。
| 登録免許税 | 資本金×0.7%(最低6万円) | 端数処理あり |
|---|---|---|
| 定款関連費用 | 認証不要 | 電子定款:印紙0円/紙:4万円 |
| 印鑑作成 | 5千〜2万円 | 電子印鑑併用も可 |
| 専門家報酬 | 数万円〜 | 司法書士/税理士パックで変動 |
| クラウド利用料 | 月額数千円〜 | 会計・請求・経費精算を一体化 |
株式会社との費用比較
合同会社と株式会社では、設立にかかる費用や手続きの内容が異なります。
主な違いを下表にまとめました。
| 比較項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税の最低額 | 6万円 | 15万円 |
| 定款認証 | 不要 | 必要(約3万円+手数料) |
| 収入印紙(紙定款) | 4万円 | 4万円 |
| 対外信用・資金調達 | 中〜高(業種依存) | 高(一般的に有利) |
設立にかかる期間(最短・標準・ゆとりスケジュール)
設立までの期間は、準備のスピードや工程の並行度によって変わります。
以下の表で、一般的なスケジュール感を確認しておきましょう。
| スピード | 目安期間 | 条件 |
|---|---|---|
| 最短 | 5〜7営業日 | 商号・目的確定、電子定款、即日申請 |
| 標準 | 2〜3週間 | 目的精査、払込、登記、口座開設 |
| ゆとり | 約1ヶ月 | ロゴ・ドメイン、会計・労務体制まで並行整備 |
合同会社設立でよくある問題点と回避策
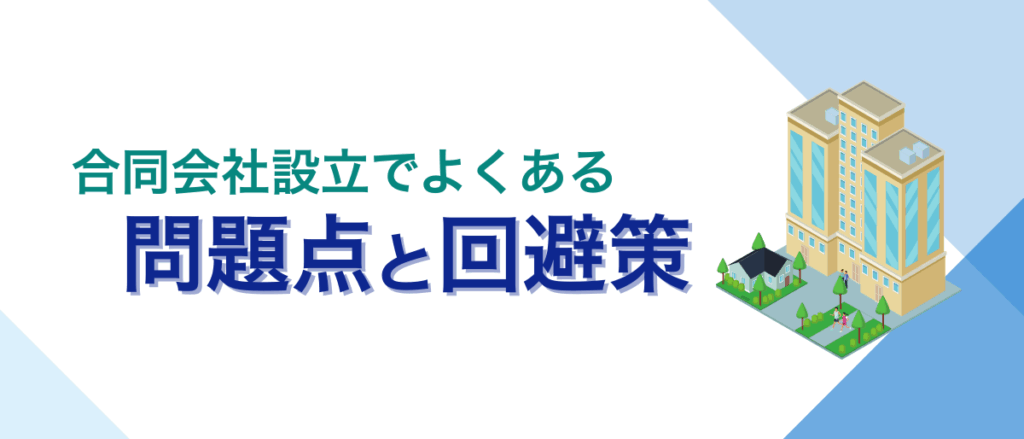
資本金の払込方法を誤り「見せ金」扱いになるケース
設立直前の大口入金→即出金は疑われやすい。
通帳の名義・日付・金額の整合を確保し、入出金履歴のコピーを保管。
事業目的が不十分で許認可が下りないケース
建設・宅建・古物商などは定款の目的文言に要件。後追い修正は時間と費用のロス。
登記や届出の遅れによるペナルティや助成金の対象外
青色承認、償却・棚卸方法、社会保険は期限管理が命。
遅延で節税・助成金・融資の機会損失も。
解決策:チェックリスト・提出スケジュール表の活用
設立から90日のガントチャートを作成し、法務局/税務署/年金事務所/労基署/ハローワークの提出物を可視化。
合同会社設立後にやることリスト
税務署・年金事務所・ハローワークへの届出
法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所の開設届出、社会保険新規適用、労働保険・雇用保険の手続き など。
口座開設・会計ソフト導入
法人口座は審査あり。
事業概要・資金の流れ・主要取引先を説明できる資料を準備。会計・請求・経費をクラウドで一元化すると月次が安定。
労務管理(就業規則・社会保険手続き)
採用予定があるなら就業規則・勤怠・給与を早期整備。社会保険の適用判断は要確認。
創業融資や助成金申請に必要な実績管理
テスト販売データ、見積・発注・契約、入金証跡を月次で保存。
助成金は事前要件(雇用契約・就業規則・保険加入)に注意。
専門家を活用するメリット
司法書士に依頼する場合の範囲と費用相場
定款作成・登記申請の一式を依頼可。
書類不備の差戻しや手戻りを防ぎ、スケジュール短縮が期待できる。費用は数万円〜が目安。
税理士に依頼する場合のメリット(税務届出・資金調達・助成金対応)
税務届出・月次決算・資金繰り・創業融資・補助金まで伴走。
会計設計(勘定科目・証憑フロー・インボイス・電帳法)を初期から正しく整えると、後の税務調査リスク低減にも有効。
自分で設立する場合とのコスト・リスク比較
| 手段 | 概要 | 向いている人 | リスク |
|---|---|---|---|
| 自分で | 最安。時間はかかる | 自力で調査・期日管理できる人 | 書類不備・期日遅延 |
| クラウド | 電子定款・書類作成ガイド | 標準的な設立ニーズ | 細かい例外対応が難しい |
| 専門家依頼 | 登記・税務・社保まで任せる | 期日厳守・融資/助成金前提 | 追加費用が発生 |
成功・失敗の実例から学ぶ
成功例:テスト販売や積立履歴を提示して融資成功
6ヶ月の積立履歴とテスト販売のCVR/リピート率を創業計画に反映。
必要額から逆算した資金計画で短期間の融資実行に成功。
失敗例:定款不備や登記遅延で事業開始が遅れたケース
目的文言不足で許認可申請が差戻し、登記も添付書類の体裁ミスで補正。
結果として口座開設・契約締結が後ろ倒しに。
学び:証跡・期日・数値計画の重要性
証跡(通帳・契約)×期日(届出・社保)×数値(売上モデル・資金繰り)の三点セットが、融資・助成金・税務の通行証。
まとめ(クロージング)
合同会社の設立は「流れ・書類・費用」を押さえれば自分でも可能です。
ただし、設立後の税務・社会保険・資金調達まで見据えると、初期設計の差がそのまま事業の走り出しと信用力に響きます。
失敗の多くは証跡不備(見せ金扱い)・期日遅延(青色/社保/労保)・数値計画の甘さです。
ここを最初に固めれば、融資・助成金・口座開設がスムーズに進みます。
最短で立ち上げたいなら、司法書士×税理士×クラウドの組み合わせがコスパ良く、安全・確実に進められます。